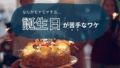インドやスリランカで5000年以上の歴史を持つ伝統医学「アーユルヴェーダ」では、白湯を飲むことで、体の働きが整いやすくなると考えられています。
本記事では、アーユルヴェーダ的な視点から白湯のメリットを詳しくご紹介していきます。
1. 白湯は「消化力(アグニ)」を高める
アーユルヴェーダでは、健康の土台は「消化力(アグニ)」にあると考えられています。
1-1. 消化力(アグニ)とは
私たちの体は食べたものを消化し、栄養を取り込み、老廃物を排出することで成り立っています。その中心的な役割を果たすのが「消化力=アグニ」です。
もしアグニが弱っていると、食べ物を十分に消化できず、栄養が体に行きわたらなくなります。その結果、消化されなかったものが「未消化物(アーマ)」となって体に溜まり、さまざまな不調を引き起こすとされます。
一方、アグニがしっかり働いていれば、消化や代謝がスムーズに進み、体は元気を保てます。
1-2. アーマ(未消化物)とは
アーマは、血液にたまる糖や脂質、関節にたまる尿酸のように、不要なものが体内に蓄積したイメージで考えるとわかりやすいかもしれません。アーマが増えると、体が重だるくなったり、眠気や意欲低下につながるとされています。
1-3. 生命エネルギー(オージャス)とは
アグニがしっかり働くと、代謝プロセスが上手くいき、プロセスの最終産物として「オージャス」と呼ばれる生命エネルギーが生まれると考えられています。
これは免疫力や生命力、内面からあふれる輝きのようなものを指します。やや観念的ではありますが、アーユルヴェーダ独自の大切な考え方です。
オージャスが満ちると、さらにアグニが強くなり、体の中に「消化力が高まる → エネルギーが生まれる → さらに消化力が高まる」という好循環が生まれるのです。
1-4. 白湯はアグニを高める
白湯は温かさによって胃腸を温め、働きを活発にします。
アグニは「炎」として表現されるため、白湯を飲むことで炎が勢いよく燃えるイメージを持つと理解しやすいでしょう。
2. 白湯は3つのエネルギーを整える
アーユルヴェーダでは、体と自然は「ヴァータ(風)」「ピッタ(火)」「カパ(水)」の3つのエネルギーで成り立つとされています。
白湯はこれら三要素すべてを含む飲み物です。
水(カパ)を用意し、火(ピッタ)で温め、沸騰の過程で空気(ヴァータ)が加わります。
このように三つのエネルギーが調和して生まれるため、白湯はどの体質(ドーシャ)の人にとってもバランスを整えてくれると考えられています。
3. 白湯でこんな不調が改善する
白湯を続けることで期待できる効果を、代表的な不調別に見てみましょう。
3-1. 便秘
便秘の大きな原因のひとつは、アーユルヴェーダでいう「ヴァータ(風)」の乱れです。ストレスや冷え、乾燥によって神経が緊張し、その結果、排泄の機能がうまく働かなくなります。
白湯を飲んで体を温めることで神経がゆるみ、排泄機能が整いやすくなるため、便秘の改善が期待できます。
3-2. 睡眠障害
「ヴァータ(風)」が乱れて神経が緊張すると、寝つきが悪くなり、眠りも浅くなりがちです。白湯を飲んで体が温まると、神経の緊張がゆるみ、心身が安らぐことで自然な眠りに入りやすくなります。その結果、中途覚醒も減り、質のよい睡眠を得やすくなります。
夜の食べ過ぎに注意
さらに、睡眠のために気をつけたいこととして「夜遅くの食べすぎ」があります。
食べすぎたまま眠ろうとすると、体は食べ物を消化するために夜中も活発に働き続けることになり、中途覚醒が起きやすくなります。これが睡眠障害の一因となるのです。
特に油を多く使った料理や肉・魚などは消化に時間がかかるため、夜は控えめにするのが望ましいでしょう。夜の食べすぎを防ぐコツとしては、昼食でしっかりと栄養を摂り、夕食を軽めに整えること。そうすることで、夜間の過食を防ぎ、睡眠の質も守ることができます。
3-3. 生理痛・PMS
生理痛やPMSもまた、「ヴァータ(風)」の乱れが大きく関係しています。ヴァータが乱れることでメンタルが不安定になり、イライラしたり「甘いものが無性に食べたい」という過食衝動が起こったりします。こうして甘いものなどを食べすぎてしまうと消化しきれず、老廃物(アーマ)が体に溜まってしまいます。この老廃物(アーマ)の蓄積が、生理痛の原因のひとつになると考えられています。
白湯を飲むことで消化力(アグニ)が高まり、アーマが溜まりにくくなります。さらに代謝が整うことで生命エネルギー(オージャス)が満ち、メンタルの揺らぎも和らぎます。その結果、生理前の気分の変動や過食衝動が抑えられ、PMSや生理痛の軽減につながるのです。
3-4. 花粉症
冬の間に小麦、乳製品、砂糖、チョコレートといった食品を摂りすぎると、消化が追いつかず、体にアーマが溜まりやすくなります。その状態で春を迎えると、花粉症の症状が出やすいとアーユルヴェーダでは考えられています。
解決法はシンプルで、アーマを溜めないことです。冬にこれらの食品を食べすぎないよう心がけることはもちろん、白湯の習慣を取り入れることで消化力を高め、アーマの蓄積を防ぐことができます。
スパイスで花粉症をやわらげる
アーユルヴェーダでは、体の不調を改善するためにスパイスを取り入れることもすすめられています。特に花粉症に関しては、以下のスパイスが役立つとされています。
・ターメリック:アレルギー反応を抑える
・コリアンダー、黒コショウ、ショウガ:アーマの浄化を促す
・フェンネル:アレルギー反応を中和する
どのスパイスもスーパーマーケットなどで手軽に手に入るものばかりです。白湯の習慣に加えて「スパイスも取り入れてみたい」と思われる方は、ぜひ普段の料理に少しずつ取り入れてみることをおすすめします。
4. まとめ
白湯は、アーユルヴェーダにおいて
①消化力を高める
②三つのエネルギーを整える
という二つの大きな働きをもつ万能の飲み物とされています。
便秘や睡眠障害、生理痛、花粉症といった不調の予防・改善にも役立つ可能性があります。
難しい理論はさておき、まずは毎朝の一杯から。白湯を飲むことで、体の内側からじんわり整っていくのを感じられるかもしれません。
5. 参考文献
・蓮村誠『病気にならない「白湯」健康法』PHP研究所、2015年
・蓮村誠『白湯 毒だし健康法 体温を上げる魔法の飲み物』PHP研究所、2010年